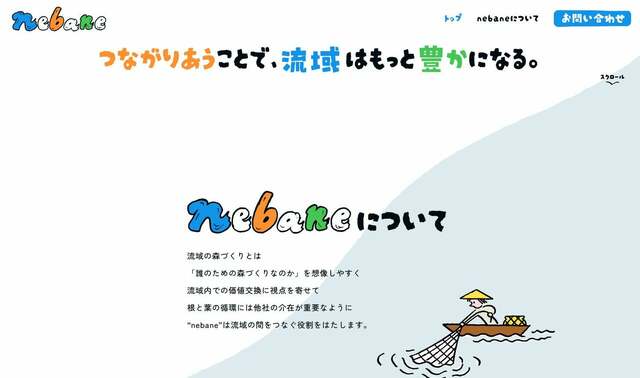長野県の最西南端に位置する根羽村は、長野県、岐阜県、愛知県を流れて三河湾に注ぐ矢作川(やはぎがわ)源流の村として、古くから流域約112万人の生活と経済発展を支えてきました。
人口は約800人、森林面積は92%。年間降水量は飯田や名古屋の約1.4倍という多雨地域で、植林されたスギやヒノキの成長は著しく、他の下伊那地方の山林には見られないような、美しい林相に目を惹かれます。
全世帯が山を所有し、村民全員が森林組合員であることも、根羽村の特徴の一つ。けれども根羽村はいま、他の中山間地域と同じように、高齢化や林業の担い手不足といった課題を抱えています。
「森と共に生きてきた村だからこそ、村民が森を“宝”だと思えるような状態を、いま、もう一度つくらないと。」そう話すのは、2018年に東京から根羽村に移住し、村のPR戦略を担当してきた杉山泰彦さんです。
根羽村ではこれまでも、森林課題を解決するために様々な活路を見出す挑戦を行ってきました。その実績が評価され、令和6年度より県の事業「輝く農山村地域創造プロジェクト」のモデル地域に採択されたことをきっかけに、3年をかけて根羽村の森の未来につながる事業づくりに本格的に挑むことになりました。
スギの木から織物をつくる"木の布”プロジェクト。
長野県では根羽村が初めて取り組みを実現。
始まってちょうど1年が経過したいま、プロジェクトはどんな地点に立っているのでしょうか。プロジェクトを先導するnebane代表の杉山泰彦さんと、根羽村森林組合の大久保裕貴さん、プロジェクト事業を受託した株式会社やまとわ取締役の奥田悠史さんに、これまでとこれからについてお話を聞きました。
彼らのリアルな葛藤と熱量を、根羽村の冬の風景とともに感じてみてください。
根羽村の基幹産業は、林業です。所有する山林から恩恵を受けてきた根羽村では、
「親が植え、子が育て、孫が伐る」という親子三代の山づくりが、
村民の哲学として受け継がれてきました。
林業での特徴は、「トータル林業」と称して、スギやヒノキを伐り出して、建築材などの生産、加工、販売までを根羽村森林組合が一括しておこなっていること。1次産業としての木材生産、2次産業としての木材加工、3次産業としての販売・利用まで村内で完結する仕組みづくりに取り組んできました。
こうした取り組みの源にあるのは、前村長である小木曽亮弌さんが2004年に打ち出した「ネバーギブアップ宣言」です。山を育て、土地を耕し、自然の恵みの中で暮らしてきた根羽村も、近代化による木材価格の低迷や産業構造の激変、そして急激な過疎化を迎えていました。
「私達は決してあきらめることなく、村民と行政が共に汗を流すことにより、誇りと希望の持てる『ふるさと根羽村』を築いていくことを、ここに宣言します。(一部抜粋)」
とあるように、国や村任せにするのではなく、村民自らが「独立自尊の精神」を大切に考え、動こう、と立ち上がったのです。
林業が衰退するなかで、根羽村でも次々と製材所が閉鎖に。村に残った最後の製材所を引き継いだのが、根羽村森林組合でした。適切な森林経営をするだけでなく、山で伐採した木を製品化し、建築用材として暮らしのなかにお届けする。根羽村の林業が伐採のみに止まらないことを見据えての決断が、いまにつながっています。
根羽村は、2017年に村周辺のほぼ全域で「森林管理の認証(FM認証)」を取得。これは、森林経営の持続性、環境保全への配慮といった基準を満たした森林が取得できるもので、村という広範囲での取得は全国でも稀なことだとか。木材加工では、信州木材認証製品として「根羽すぎ」「根羽ひのき」の製品ブランドで工務店に直送販売をしている
林業への信念と、本気だからこその葛藤
根羽村森林組合に10年以上勤める大久保裕貴さんは、「伐採や加工、環境保全プロジェクトなどに加え、村民や子どもたち、流域のみなさんを対象とした木育活動や環境教育もおこなってきた」と話します。ただ、実際に取り組む中での現実の壁に多くぶつかってきました。
根羽村森林組合 大久保裕貴さん
大久保裕貴さん
「大きなやりがいはあるものの、目の前のことをクリアすることに、それぞれが一生懸命で。根羽村の森にどうつなげていったらいいんだろう、どこに向かったらいいんだろうと、ビジョンを考える呼びかけを、地域おこし協力隊として林業を始めた山本英介さんと昨年、組合内でしてみたんです。いろんな意見は出たものの、結局、かたちにはなりませんでした(苦笑)。」
根羽村の森を、どうしていくか。森林組合は、どこを目指すのか。組合は、職員のトップにあたる参事の交代という転換期を迎えていました。大久保さんは、まずこうした動きをしていいか組合内で承認をもらい、コアメンバーになってくれそうな人や事務員、現場メンバーも含めて、どう進めていいかわからないまま半年ほどかけて手探りで議論を重ねました。そうしているうちに、他にもっとやることがあるのではないか、という意見も出てきたのだとか。この悩みを杉山さんに共有したところ、「輝く農山村地域創造プロジェクト」を通じての解決案を提案されたと言います。
杉山泰彦さん
「一般社団法人ねばのもりでは根羽村役場と共に矢作川源流の水と森を守る環境保全プロジェクトをこれまでも推進してきました。森の大切さを知り、森を守らなければ、水は守れない。企業版ふるさと納税等も活用しながら企業や下流域の人々との共創によって、水源と水を守ることを目指してきました。村や木の魅力をより多くの人に伝えて、 森を守る行為を事業にすることを僕ら森の民のミッションの1つとしてきたんです。」
一般社団法人ねばのもりでは村をフィールドにした体験プログラムをこれまで数々実施。流域沿いの企業や子どもを中心に2024年は累計500人近くの受け入れを行い、森や里山の魅力、水源の大切さを伝える活動を行なっている。
「村民が、何があったらこの村を誇りに思うかって、やっぱり森が元気になることだと思うんです。でも林業は基幹産業で歴史も長く、いろんな人たちが絡んでいるので、強引に進めると分断が生まれてしまうかもしれない。だからこれまで、森林組合の部外者である私は林業ではなく森林サービス産業を手掛けてきました。でもやっぱり森が元気になるには森林組合が元気にならないと、と思っていたときに裕貴さんから悩みの相談をもらって。これは最後のチャンスだと思ったんです。このタイミングでやらなかったら本当にまずい、火が消えてしまいそうだな、と。」
火が消えてしまったら、つけ直すのは相当難しい。森林組合内でビジョンを考えようとしてうまくいかなかったタイミングと、県の事業「輝く農山村地域創造プロジェクト」に採択されたタイミングが重なったことから、杉山さんは「輝く農山村地域創造プロジェクト」で、村の森林のあり方を検討することを役場に提案しました。
一般社団法人ねばのもり代表理事/nebane代表の杉山泰彦さん。あだ名はマギー
杉山泰彦さん
「見渡す限り森であるという村の資源を、価値がないと捉えるのか、まだ価値があると捉えるのか。いまは、森を宝だと思う人は少なくなってしまったかもしれないけれど、みんなが宝だと思うようになったら、どれだけワクワクするか。村が森林組合の経営を担い、山の所有者もわかっていて、流域というマーケットもある。それが強みであり、その強みをもう一度尖らせる意味はあるのではないかと、役場担当者はもちろん、県担当者とも議論を重ねました。」
とはいえ「輝く農山村地域創造プロジェクト」の1年目のマイルストーンをすぐに具体的に整理するのは難しかったのだとか。そこで、信州大学農学部農村計画学の内川義行准教授に相談することに。根羽村と信州大学農学部は連携協定を結んでおり、中山間地域の新たな土地活用として山地酪農の意義や課題を探るなど、地域資源を活用した持続可能な村づくりを共に推進してきました。
杉山泰彦さん
「信州大学も一緒に何かできませんかと内川先生に相談したら、快諾をいただくとともに、ぜひやってほしいことがあると言われて。村民を巻き込むことはもちろんだけれど、関係者への聞き取り調査なども踏まえて、しっかりと現状把握をした上でビジョンをつくってほしいとアドバイスをいただきました。聞き取り調査をするなかで、共感してくれる仲間ができたりするかもしれないと。」
そこで、「輝く農山村地域創造プロジェクト」の1年目は現状把握のための時間にすることになり、根羽村はプロジェクト事業の受託先を募集。プロポーザルの結果、事業を受託することになったのが、長野県伊那市で「夏は農業、冬は林業」という複合経営をする、株式会社やまとわでした。
「自然への知識や経験」に「編集やデザイン」を組み合わせて、自然と社会をつなぎ直す事業を手掛けている株式会社やまとわの奥田悠史さんは、根羽村に通い、村民や林業関係者への聞き取り調査を始めました。
株式会社やまとわ 取締役 奥田悠史さん
奥田悠史さん
「関係者がどんな思いをもっているか、どんなふうに現状を捉えているか、8人ほどお話を聞きました。それぞれ、すごく真面目に森のことを考えていて、自分にしかできない仕事をしようとしている。みんないい人で、思いがあって、なんというかすごく好きになる。でも、どこかうまく歯車が噛み合っていない部分もありそうだと感じました。歯車が噛み合ったら、相当面白い。だから、地域としてどう強さをつくって、そこに森林組合が乗っていくかだと思いました。」
根羽村の強みをどう捉えるか。インナーブランドも含めて、根羽村というブランドをどうつくるか。奥田さんからの提案は、誰のための森づくりなのかをイメージしやすくするために、流域での森づくり、流域での価値交換に視点を寄せた「流域がつながり合う経済圏をつくる」ことでした。
奥田悠史さん
「ないものをつくるのは、無理じゃないですか。例えば家具のプロダクトをつくりましょうといっても、広葉樹の製材所もなければ、家具職人もいない。だけど、この地域には、針葉樹の製材まで手がける森林組合があって、さらに山地酪農をする幸山明良さんや、マギーさんみたいな、体験をもとにしたコンテンツをつくれる人たちがいる。いまある強みをつないで価値に変えるには、いまいる人たちがしっかりとワークすることが一番大事で、もともとある下流域との経済交流に絞るのがいいのではないか、と考えました。矢作川流域の人たちにとって、根羽村はどんな価値を提供できるのか。源流域の環境保全のための寄付といったかたちでは、イーブンな関係性をつくりにくい。まず根羽村から下流域に対して価値の提供をするという順番が大事だと思うんです。」
矢作川流域の上流と下流で価値を交換して、生活、文化、経済が生まれる流域経済圏をかたちづくること。杉山さん、大久保さんはもちろん、提案を受けた根羽村役場も「そうですよね、やっぱりそこですよね」と満場一致で進めることに。
さらに奥田さんは、根羽村森林組合に対して、住宅一軒分のカスタムオーダーメイドを得意とする製材所となることを目指しつつ、オーダーを待つのではなく、暮らしやすい設計、住みたくなるデザインとともに販売を仕掛けることを提案。こだわりのある設計士の思いに200%で応えることのできる小規模製材所というブランドづくりを提案しました。
加えて、こうしたプロジェクトを村内で推進していくための新会社が必要、とも。事業のコンセプトを握り、企画を生み出し旗振りをする存在として、3年後の2027年には5人くらいのチームを目指すことに。森林組合と連携して矢作川流域での認知を広げながら、地域のおじいちゃんおばあちゃん、子どもたちが縁側で苗木をつくる「縁側苗木づくり」を通じて、村民を森づくりに巻き込もう、という提案もありました。
奥田悠史さん
「プロジェクト名は、『nebane』という案を出しました。根を張り、葉が茂り、自身の養分をつくる葉が落ち、分解され、土の養分になる。根と葉の循環には他者の介在が重要で、nebaneはその間をつなぐ役割である、という位置付けにできたらと。Webサイトは、あえて可愛らしいイラストを用いたポップなデザインで、森や流域を絵本のように表現したいと考えました。」
nebaneのWebサイトは5月に本公開予定。
ティザーサイトは既に公開されており、段階的に更新される予定
森を表現しようとすると、神秘的で神々しい世界観になりがちですが、その要因はクリエイターの自然への解像度が低いからではないか、と奥田さんは指摘します。
奥田悠史さん
「地域ごとに見なくてはいけないはずの森が、どこも同じように”神秘性”みたいな側面に逃げられていると感じているんです。その世界観だと、森が近寄りがたい存在になってしまう。僕らは毎日森に向き合っていて、もっと解像度は高いはずです。森は、もっとポップでいいし、いじってもいい。それが、マギーさんらしいかなと思いました。マギーさんも裕貴さんもいじられるキャラクターなので(笑)。神秘性ではなく、身体性やキャラクター性に近いデザインにするほうが、根羽村の森が動き出すのではないかと思ったんです。」
熱量さえあれば、できることは無限にある
プロジェクトの一環として、2025年2月には、根羽村村民と流域の人たちを主な対象に、流域がつながり合う経済圏を考える全3回のトークイベント「根羽村 森とまちの流域学」を開催しました。
第1回は「杉の森から考える流域の森づくり」をテーマに、一般財団法人もりとみず基金の尾崎康隆さん、フォレスターズ合同会社の小森胤樹さんが登壇。第2回は「森を次につなぐ -ものづくり 事業づくり-」について、株式会社nojimokuの野地信卓さん、QUSUYAMA LLC.の吉水淳子さん。そして第3回は「豊かに生きる -森と村-」について、うきはの宝株式会社の大熊充さん、ハッピーマウンテンの幸山明良さんが話しました。
杉山泰彦さん
「主催側の僕ら自身が、すごく面白かったんです。こうありたいよねという事例や、こういうふうに考えてみたいよねという題材、描いている構想を補強してくれるような話が出てくる。村民たちが一緒に聞いてくれていることが、めちゃくちゃ大事ですよね。流域からもたくさんの人たちが来てくれました。」
第2回は、事前にnojimokuさんを視察してからイベントに臨んだのだとか。どの回も大きな学びがあったけれど、大久保さんにとって、製材の実践者に来てもらい、自身やビジネスの経験をもとにしたアドバイスを受けたことは、組合内に大きな影響を及ぼした、と言います。
大久保裕貴さん
「他の製材所を見学させていただく機会って、これまでになかったんです。そもそも製材って難しいですよね、という共感もありましたし、とても腑に落ちたところがあって。野地さんは家業として、僕たちは村としてやっているという違いはありますが、何かしら連携が生まれそうな関係性がつくれたこと、語り合える仲間ができたことが何よりも嬉しかったです。」
杉山さんは、「裕貴さんの目が輝いた瞬間があった」と話します。
大久保裕貴さん
「そう、僕らも、まだいけるかもって思うことができたんです。もうだめかもって思ったこともあったかもしれない(苦笑)。圧倒的な設備の差があるわけではないんです。同じような設備だけれど、地域の強みを生かしてアイデアで勝負をする、そこで頑張っているのを見て、自分たちも頑張らないと、と思いました。」
一緒に視察に行った職員たちは、森とまちの流域学が開催された日の翌朝、自主的に対話の時間をつくっていたのだとか。大久保さんは「さっきの奥田さんの話でいうと、歯車が合うってこういうことかと思った」と続けます。
大久保裕貴さん
「僕だけが空回りしていたんじゃないんだ、と思いました。他の職員も、何かしらのスイッチが入ったんだなあと。職員が、この歯車と歯車の溝をどうやって埋めたらいいですか?と野地さんに質問する場面があったんです。そうしたら、それはたぶんずっと埋まらないと思う、熱量を上げるしかないって。それを聞いて、もっと熱量を上げていかないと、ってみんな感じたんだと思います。できることは、無限にあるはずですよね。」
自分一人だけでなく、仲間とともに熱量を上げていく。その熱を飛び火させることができれば、大きな変化につながりそうです。
奥田悠史さん
「歯車と歯車の間に、何かを追加するのか、自分の歯車を大きくするか。もちろんこれまでも頑張ってきたと思うんですが、そこでさらに、自分たちは本当に頑張っているのかという問いをもたないと、この衰退産業のなかで生き残るのは難しい。それこそ、だめかもしれないというところから、いけるかもしれないと思えるようになるには、実際には人一倍の努力が必要だったりする。そのスイッチが自主的に入るって、素晴らしいですね。」
杉山泰彦さん
「森とまちの流域学が終わった後の、飲み会の風景がすごく嬉しかったんです。視察に行った時もそうですが、森林組合の人たちが、こういう場に出てくれて、懇親会でも、すごく楽しそうに話をしていました。外部からエンパワーメントしてもらって、変わっていく兆しが、流域学の2回目にして、もう見えてきたなと。」
杉山さんが「そういう変化が生まれていくこの村って、すごいと思う」と言うと、奥田さんは「みんないい人だから」と返し、大久保さんが「素直なんですよね、そのまま受け取っちゃう」と重ね、一同で笑いました。
「流域」にフォーカスして動き始めた流域経済圏プロジェクト「nebane」。これからやりたいことをお聞きすると、杉山さんから「たくさんあるけれど、いろいろな人とパートナーシップを結びながら事業にしていくことが大事だと考えている」と返ってきました。奥田さんも「雇わないと生まれない価値がある」と言います。
奥田悠史さん
「みんなの余白を集めるだけでは足りないんです。他に本業を抱える人が森に関わるだけでは、どうしようもないぐらい難しい。本気でやろうとするからこそ生まれる価値がある。業務委託を考えるとイメージしやすいと思うんですが、この部分をお願いしますという依頼では守備範囲がせばめられて、守備範囲と守備範囲の間を見落としたりする。それは失点のリスクになるけれど、本気で守り抜くという気持ちがあってはじめて、隙間から転がってくるボールが取れるし、それがチャンスに変わる。だから、人を雇うという熱量がチャンスを生むと思うんです。それが、根羽村において達成されるべきことなんじゃないかと。」
根羽村が「輝く農山村」であり続けるために、本気で面白い仕事をつくるということ。さらに奥田さんは「雇用のいいところは、スペシャリストじゃなくても生きていけること」と続けます。
奥田悠史さん
「村って基本的に百姓が多いですが、移住者は必ずしもスペシャリストではない。村には、事務的な仕事が得意という人が生きられる場所は多くはないですよね。個人事業主の集まりでも、実現できるかもしれませんが、売り上げが立ちづらい場所に売り上げをつくるには、熱量の集まりというか、突破しないといけないものがあると思います。」
では、どんな面白い事業をつくるか。杉山さんは「あれもやりたい、こんなこともできるねと、昨日も村のメンバーと深夜2時まで話した」と言います。
杉山泰彦さん
「具体的なプランの一つは、『つくる』と『つかう』が循環する、いわゆるサーキュラーエコノミーの仕組みをつくることです。根羽村でつくったものを購入してもらうと、その何%が流域保全に使われる、といった仕組みを考えています。また、矢作川流域とも、ガストロノミーのような一日限定のイベントを開催するなど、「食」のつながりをつくれないかと考えています。腕利きのシェフをお呼びして、根羽村の森の食材や流域沿いの食材を使ってつくってもらう。まずは、わくわくしながらこの流域沿いにある文化の魅力を感じる機会をたくさんつくっていきたいですね。」
大久保さんにも、これからやりたいことを聞いてみると、こんなふうに答えてくれました。
大久保裕貴さん
「いろいろあるけれど、新しいことにチャレンジするというよりも、森林組合の経営や事業に集中して、一つひとつを磨き上げていきたいと思っています。これまでは、何か始めたとしても、どうせ変わらないでしょ、みたいな空気感があったかもしれないけれど、今回は違うよ、と打破したい。だからどんどん職員を巻き込んでいきたいと考えています。」
大久保さんの話しぶりは、とても穏やか。でも、内面には炎が燃えているのだ、と思いました。そう伝えてみると、杉山さんから「そう見えないでしょ。でもね、昔から口癖は“稼ぎたい”だから(笑)」とつっこみが入ります。
大久保裕貴さん
「あきらめないことが大事なのでしょうね。僕らには難しいとか、無理かもしれないとか、途中であきらめたくないんです。 」
根羽村は、村民一人ひとりが森のことを語れるといいます。
村のみんなが大事にしてきた森を、「ネバーギブアップ」という、あきらめない心を携えて、これからも大事にしていくということ。
「流域」や「経済圏」といった言葉が気になる人は、ぜひ根羽村へ足を運んで、村の人に会ってみてください。そして、流域経済圏プロジェクト「nebane」が開催するイベントやワークショップに参加してみてもらえたらと思います。その小さな一歩があちこちで支流を生み、より大きな流れをかたちづくっていくのです。
nebane公式ティザーサイト: