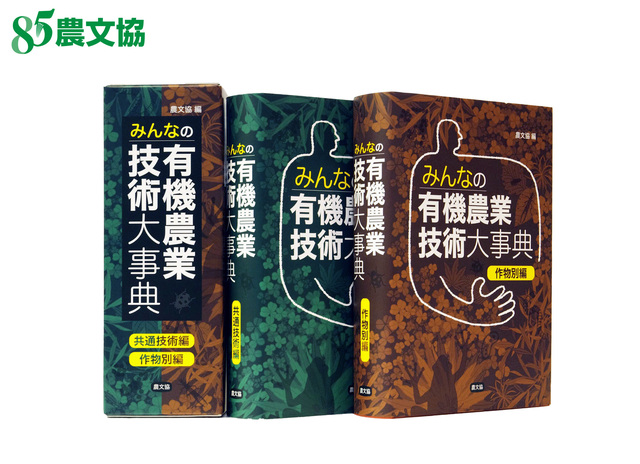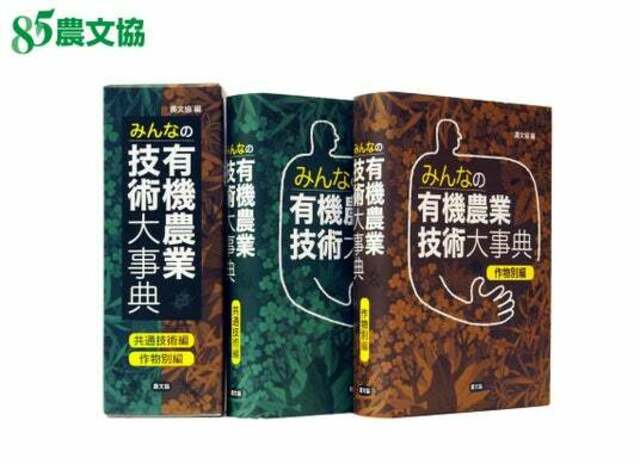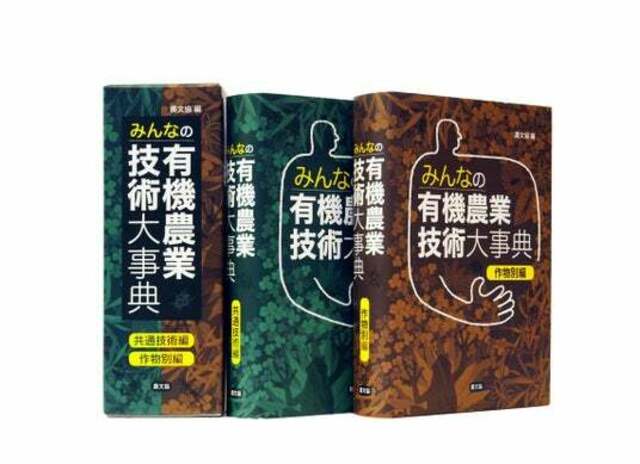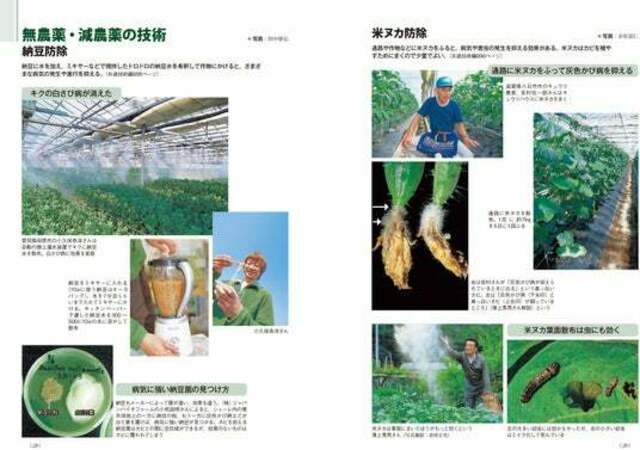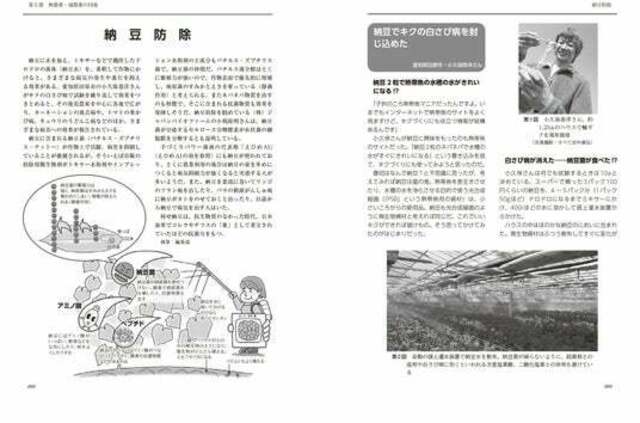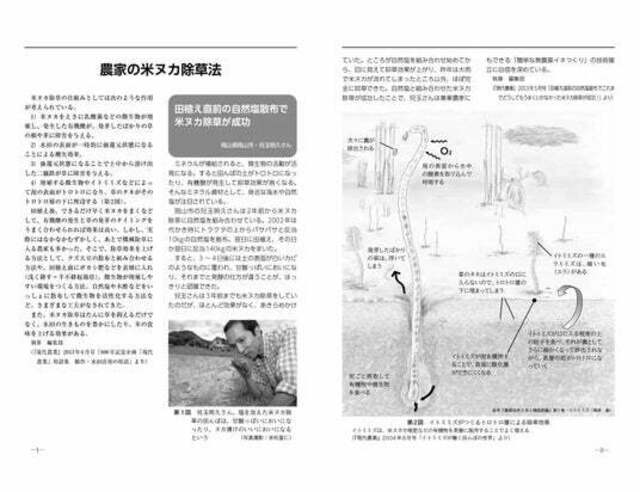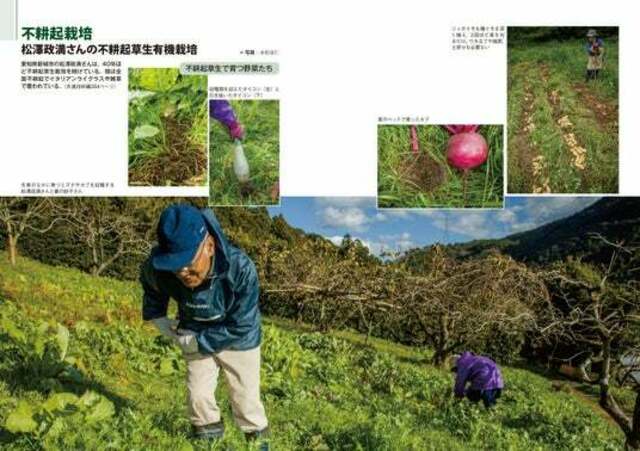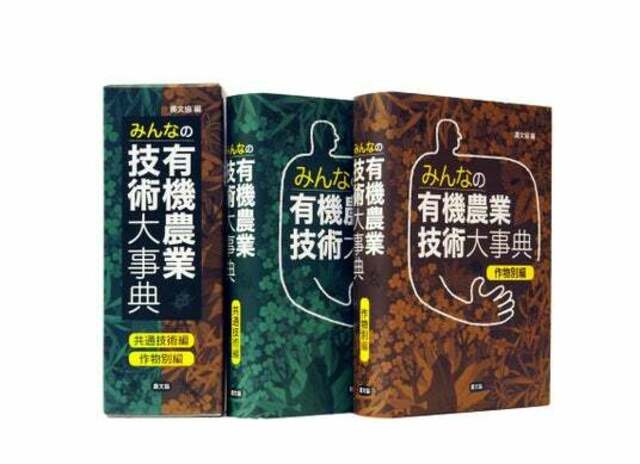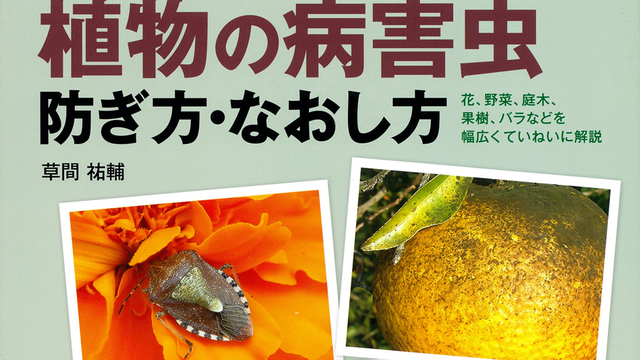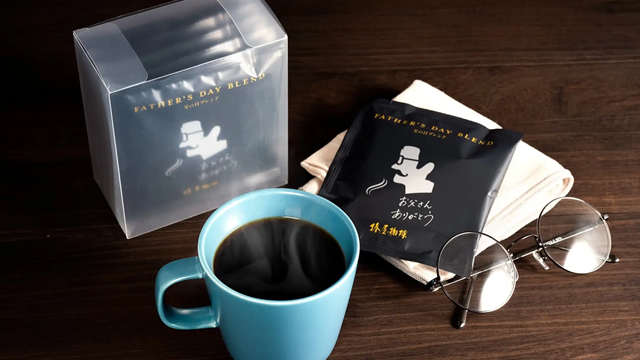CHANNEL
- HOME
- 新着記事
- ファッションのイマ for Her
- ファッションのイマ for Him
- おいしいものを毎日食べたい
- 大人のキャンプ&外遊び
- 次の旅先どこにしよう?
- 休日お散歩
- クルマが好き
- 今欲しい最新ガジェット
- 作りたくなるレシピ集
- 役立つライフハック
- サステナブルなくらし
- あげるのが惜しい手みやげ
- 星野リゾート 日本旅
- 最新トレンド情報まとめ
- 知りたいビジネスストーリー
- ARTICLES IN ENGLISH
- 絶対行きたい美術展ガイド
- ゆらぎ肌にまけるな!
- おいしいドーナツが食べたい
- あの人も実践!インナーケア
- 感動ギフト、ここにあります
- I ♡ YKNK(ヤキニク)
- ととのうサウナ
- 今アツいK-Culture
- オトナのゆったり酒場
- 「血管」をととのえる
- いい靴下、履いてますか?
- 大谷翔平おっかけ隊