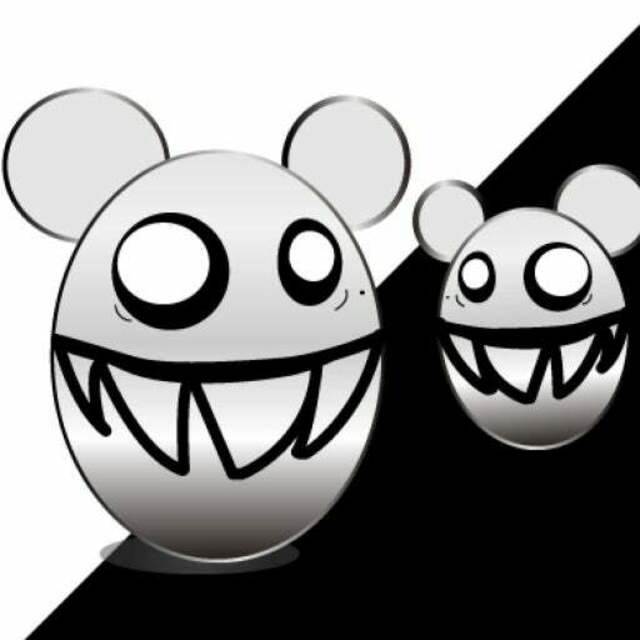すでに成熟した市場とされる日本においては、代替製品の多様化により競争が激化し、消費者のニーズも一層多様化・細分化しています。このような環境下で、「消費者の心を掴むための独自の優位性」を見出すことが、企業の生き残りを左右する重要な戦略課題となっています。この課題を解決するための一つの手段として生成AIが注目されており、生成AIをどのように活用して競争優位性を確立し、消費者の多様なニーズに応えるかが重要な論点となっています。
今回は、企業の顧客理解における課題解決に向けてシナジーマーケティング(以下、当社)が提供する「DAYS GRAPHY」の開発秘話をご紹介します。新しいプロダクトを企画・開発するなかで、昨今話題となっている生成AIをどのように取り入れて価値を生み出してきたのか、エンジニアの松浦さん、田中さん、デザイナーの山本さんを中心に、プロダクトオーナーの阪口さん、UXプランナーの多久さんも交えてお話を聞きました。
■DAYS GRAPHYとは
顧客の日常や生活状況を深く理解することで顧客のまだ満たされていないニーズを捉え、商品企画やマーケティング施策のアイデアを生み出しやすくする日常描写型顧客理解システム。口コミやレビューコメントをインプットするだけで、日常や生活状況が描かれている顧客像を最短10分で生成。さらに、チャット機能を使った対話を通じて顧客理解を深め、商品開発やマーケティング施策などにつながる具体的なアイデアの想起をサポートする。
■プロフィール
阪口 奨 / クラウド事業部 サービスデザインG マネージャー
2008年新卒入社。入社以降15年一貫して営業をしたのち、新規事業担当となりDAYS GRAPHYを企画し、プロダクトオーナーとしてサービスの普及に邁進中。
多久 南美子 / クラウド事業部 サービスデザインG
2007年新卒入社。クラウド型CRMシステム「Synergy!」の設定代行業務やサポート業務、デジタルマーケティングのコンサルティングなどを経て、DAYS GRAPHYのUXプランナーを務める。
松浦 亮 / プロダクト開発部 第4プロダクト開発G
2015年新卒入社。エンジニア。主にクラウド型CRMシステム「Synergy!」の保守・機能開発に携わる。DAYS GRAPHYでは、主に生成AI技術まわりを担当。
田中 賢樹 / プロダクト開発部 第2プロダクト開発G マネージャー
2019年中途入社。エンジニア。DAYS GRAPHYでは、主にフロントエンジニアを担当。
山本 信幸 / プロダクトデザイン部 プロダクトマネジメントG
2018年中途入社。HCD-Net認定 人間中心設計専門家。DAYS GRAPHYでは主にUXリサーチやUI設計を担当。
※部署名・役職は取材当時(2024年12月)のものです。
生成AI技術の登場で、行き詰っていた企画が一気に前進
── DAYS GRAPHYの企画が始まった経緯を教えてください。
阪口:
きっかけは、2022年に新規事業創出を目的とするグループに配属されたことです。その一年前の2021年に当社のビジョン・ミッション・バリューが刷新されたんですが、ミッションの「Create Synergy with FAN」(※1) に相応しい新たなサービスを提供したいと考えました。
「Create Synergy with FAN」を説明した文章の中には「生活者と企業がお互いにファンと言い合えるような関係性を築き」という部分があるのですが、サービス開発のために企業が抱える課題をいろいろと調べているなかで、ファンと言い合えるような関係性を築く以前に、「世の中の企業の半分以上が、そもそも自社の顧客理解に課題を感じている」というデータに出会いました。当社はCRM領域に強みを持っており、ニーズが顕在化しているクライアントには一社一社個別に顧客理解のソリューションを提供してきましたが、まだまだ多くの企業が課題を抱えていることに気づきました。この課題こそが、創業から20年以上に渡ってCRM領域を専門にしてきた当社がソリューションを提供すべきだと考え、本格的に企画がスタートした経緯です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(※1) 「生活者と企業がお互いにファンと言い合えるような関係性を築き、そのつながりから生まれる価値を通じて、新たなマーケットを生活者や企業と共に創り出していく」という意図を込めたミッション。詳しくは
── 2022年の時点ではまだ生成AI技術は登場していませんでしたが、どのような道のりでサービスリリースまで辿り着いたのですか。
阪口:
まずは、顧客理解における課題の解像度を高めるために、有志の企業様に協力いただき、消費者インタビューを中心とした企業が行う顧客理解のプロセスを改めて自分たちで体感するところから始めました。並行して、サービスの方向性や骨子などを多久さんと話し合い、試行錯誤を繰り返しました。
いろいろとサービス案は出てきたのですが、コスト面やマネタイズ面が特に悩ましく、途中で行き詰まってしまったんです。ですが、そのタイミングでChatGPTが登場し、自分でいろいろ触ってみると、ちょうど自分たちが考えていたことが低コストで実現できそうだということに気づきました。まさに奇跡的なタイミングでした!それが起爆剤となり、「生成AIを活用した、顧客理解を深めるサービス」を一気に具体化することができたのです。さっそく上長に相談したところ、すぐにGOが出て、エンジニアの松浦さんの参画も決まり、2023年10月にプロトタイプ版の開発がスタートしました。
松浦:
初めて触れるものだったので、開発に着手するにあたって、まずOpenAIから提供されているAPIがどのようなものであるかを確認し、試行錯誤しながら作っていきました。阪口さんや多久さんから「口コミをシステムに取り込むだけで、顧客像が生成されるようなものを作ってほしい」という要望だったので、どのような機能のシステムにするのが適切かを考えながら進めていきました。
多久:
松浦さんに要望を伝えてから2か月ほどの短期間で、システムの設計から実装までを対応してくれました。松浦さんは「作りが粗いところもありますけど……」と言っていたんですが、私が見た限り、見た目や操作感はほぼ要望通りの状態にできあがっていて。あまりの速さと完成度の高さにとても驚きました。
超高速で開発が進んだおかげで、2023年12月からプロトタイプを活用した価値検証を進めることができ、2024年1月にはUI/UXを担当するデザイナーの山本さんとフロントエンジニアリング部分を担当するエンジニアの田中さんが参画、2024年8月にサービスをリリースすることができました。
── 生成AIは誰にとっても初めて扱う領域だったと思いますが、非常にスピード感がありますね。実際の価値検証に参加されたお客様からの反応はいかがでしたか。
阪口:
価値検証には20社ほど参加いただいたのですが、ありがたいことに総じて大変良い反応をいただきました。一例ですが、「今までは、人手をかけ、多くの時間を使って作成していた顧客像が口コミデータだけで瞬時に生成できるので、圧倒的に効率化できた。さらに、その顧客像とトーク機能を通して自由に対話できるので、知りたかったニーズの背景にある状況を回答として引き出せる。インサイトの発見に大変有効で、今後のマーケティング施策や商品開発などのアイデアについてとても考えやすくなることが期待できる」といったお言葉をいただいています。
現在導入いただいているお客様はメーカーやブランディング支援をされている企業が中心で、企業規模は大小さまざまです。開発当初は、当社のマーケティングSaaS「Synergy!」(※2)の主要顧客である、販促やWebサイトの運用をされているお客様のご利用を想定していたのですが、実際は、マーケティング領域はもちろんのこと、ブランディングや商品企画に携わるお客様からも高い関心を寄せていただいています。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(※2)集客、顧客情報の統合・一元化、クロスチャネル・メッセージング、分析まで、企業のマーケティング活動を支えるCRMから進化したマーケティングSaaS。詳しくは
前例がない領域だからこそアグレッシブに!開発のPDCAサイクルは超高速で回す
── 開発するにあたって、「3日で作って触ってみて、駄目だったら捨てて次を試す」という進め方をされたと伺いました。
多久:
前例のない最先端技術を活用したサービスなので、とにかく試行錯誤の回数を増やして改良を重ねることに重きを置きました。週一回程度の頻度で山本さんと田中さん、私の3名で議論する場を設け、高速で「アイデア出し→試用→分析→改善」のサイクルを回し続けました。バックエンドの修正が必要な場合は、松浦さんにも参加していただいていました。
議論しているときは良さそうに思えたアイデアも、いざテスト画面を作って触ると違和感がある、なんてことも多いんです。そういう感想をお伝えすると、山本さんや田中さん、松浦さんが「では、こんな感じはどうですか?」とサクッと提案・修正してくださるので、とても心強いです。とにかく皆さんめちゃくちゃ仕事が速い……!
田中:
常に「いかに検証のサイクルを早く回すか」を意識しています。具体的には、議論のスピードや質を阻害せず、スムーズに開発を進めるために、「ひとつのアイデアに固執せず、すぐに捨てられる状態」をキープするように心がけました。初期段階から、松浦さんが高い質とスピード感を持って開発されていたこともあり、そのラインを維持するのはもちろんのこと、フロントエンドとして価値貢献できる部分を深く追求していました。
山本:
当社のサービス開発としては異例のスピード感かもしれないですね。私は「Synergy!」のデザインも担当しているのですが、開発プロセスが真逆なんです。Synergy!は、約20年に渡って提供していて多くの利用者がいるサービスなこともあり、「お客様が求めているニーズや抱えている課題感が何であるか」をしっかり調査したうえで言語化しながら開発しています。一方で、DAYS GRAPHYはとにかくまずは作ってみる。「できあがったものがロジック的にしっかりしていても、実際に触ってみて違和感があればそれは求めるものとは違う」という認識で進めています。考え方が真逆なので、Synergy!とDAYS GRAPHYを同じ日に両方の作業を進めると頭が混乱してしまう(笑)
── 職種に関係なく「何を重視すべきか」の認識が揃っているからこそ、実現した高速開発なのですね。
田中:
そうですね。あとは、雰囲気作りというか環境作りも重要だと思っていて。開発側からすると、営業やディレクター側にアイデアがないと動きようがないですし、営業やディレクター側からすると、開発に依頼しても「工数がなくてすぐに動けない」と言われると企画の進行がストップしてしまいます。どちらも「とにかくいろいろ試してブラッシュアップしていきたい」と考えているのに、できない理由を並べて難色を示されるとモチベーションは落ちていきますよね。こういった悪循環に陥らないように、阪口さんや多久さんから要望が来たら、2日後には開発側から実際に触ってもらえる形で提案できるように留意していました。「打てば響く状態にすることでお互いのモチベーションが高まり、活気のある開発サイクルになるのでは」と考えたんです。私自身もこのような環境が実現したことで、開発がとても楽しく感じられました。
加えて、松浦さんがシステムの基盤を綺麗に作ってくださっていたことも大きいですね。要望に対して改修すべき部分が明瞭なので、素早い改修が可能になっています。
松浦:
田中さんが挙げた点にプラスして、「いかに多くのお客様が利用したくなるシステムにするか」の観点も重視していました。どんなに画期的かつ優れたシステムを作ったとしても、誰にも利用されなければ意味がありません。
多久:
松浦さんたちが「試してみて違ったら捨てる前提で作っているから」と言ってくださったおかげで、気兼ねなくこちらの要望を伝え続けることができました。私たちの要望をシステムに落とし込むだけでなく、利用するお客様のこともしっかり意識しながら開発していただけたので、とても心強かったです。お客様に対する考え方や目線も合っていたので、非常にスムーズに進みました。
阪口:
開発側に要望を出していくなかで、私自身もいつの間にか目的がずれてしまうこともありましたが、そんな時は必ず、「これは何のために作るのか?」という問いを返してくれました。質が高く速いだけでなく、サービスの軸がブレないように進められたので助かりました。
── デザイン面でこだわった点についても教えてください。
山本:
阪口さんと多久さんの構想をイメージ通りに形にしていくこと、かつ利用者にとって違和感を生じさせないものにすることにこだわりました。DAYS GRAPHYは業務システムなので、「誰でも違和感なく、滞りなく操作できるかどうか」が重要です。そのため、デザインは極力シンプルにしました。見栄えの良い画面を作る方法は多く存在しますが、今回は意図的に選択肢から外しています。
一例を挙げると、生成AIが出力した結果画面に対してあえてデザインで色付けをせず、全体をモノトーンでまとめています。これは、管理画面に色が入ると生成AIで出力した内容の印象を操作してしまうので、利用者の顧客理解に影響を与えてしまうためです。出力結果を余計な情報で脚色してしまわないように工夫しました。シンプルであるが故の難しさはありましたが、頭を悩ませた甲斐はあったと思います。
田中:
あわせて、画面操作にも細かくこだわりました。「マーカーを引く」という動作機能を例に説明すると、マイクロソフトのWordは「メニューから機能ボタンを探す→押す→マーカーが引かれる」という工程で操作できますが、2024年12月現在のDAYS GRAPHYにはそのようなメニュー配置がありません。そのため、「ここ重要だから線を引きたい」という直感に基づいたユーザー体験をどのように作り出すべきか、議論と検討を重ねました。4〜5回くらい作り直したかな。
山本:
あれは結構悩ましかったよね(笑)。Wordに倣ったマーカーの引き方も検討したんですが、いざ操作してみるとどうにもしっくりこなくて。DAYS GRAPHYで必要とされるのは文章の校正を目的としたマーキング機能ではないので、用途にあった新しいインターフェースを考える必要があって。「しっくりこない」と感じる理由をチーム内でまずは言語化して、幅広く検討しましたね。
開発者である私たちが触って違和感があるものは、当然ながらお客様も違和感を感じます。そのため、「私たちが自然かつ気持ちよく操作できるかどうか」をひとつのラインとして設計しました。「使いにくい」という理由でサービスの価値を下げたくない気持ちが強かった一方で、当時は生成AIを活用したプロダクトがまだ世に出ておらず、当然ながらUIも見たことがなかったので、毎日が本当に手探りでした。
生成AIを、業務効率化ツールではなく ”新しい価値の探索ツール” として活用する
── 今後のDAYS GRAPHYの展望について聞かせてください。
阪口:
DAYS GRAPHYは、表面上は「簡易ペルソナ生成ツール」と捉えられがちですが、人物像の生成はあくまでも最初の1歩であり、その人物像の日々の営みを深く知ることで自分たちが見落としていたインサイトを発見し、そこからアイデアを生み出せることが本質的な価値だと考えています。そういう点では、実在する人物にインタビューをして得られるインサイトを100点とした時に、80点ぐらいまではDAYS GRAPHYで引き出せるようにしたいと考えています。
また、顧客理解というジョブのゴールは「人を知ること」ではなく、そこから「今までとは違うアイデアを生み出すこと」なので、アイデアを創出しやすくなる仕掛けももっと増やしていきたいと考えています。そのためには生成される内容はもっとリアリティのあるものにしていくことが必要不可欠なので、実現に向けたチャレンジを続けているところです。
直近では、チャレンジの一環として、三田市教育委員会様の実証事業である「MIRAIノートプロジェクト」に参画しています。このプロジェクトは、小学校高学年以上の学年で一割程度いると言われる「困ったときに誰にも相談しない」という児童生徒に対して、新たなコミュニケーションの場を創出するためのAI対話アプリ「MIRAIノート」を、一部の学校に試験的に提供する、といったものです。コロナ禍で人との交流機会が不安定となり、対話に不安を感じる子どもたちに、安心して対話できる環境を提供することで、コミュニケーションの練習をしながらリアルな対話にも気兼ねなく挑戦できるように促すことを目的としています。2025年1月9日より提供を開始しています。
松浦:
今後も、阪口さんや多久さんが思い描く機能を実装するために、生成AIについて学びながら開発を続けていきます。LLM(Large Language Models;大規模言語モデル)と一口に言ってもさまざまな技術があるので、それらを適切に組み合わせることでサービスの体験価値の向上を実現したいですね。
田中:
私はフロントエンドを担当しているので、お客様がDAYS GRAPHY内での操作をスムーズに遂行できるように工夫・改善を続けていきます。現在は、サービスリリース後の一旦開発が落ち着いているタイミングなので、今のうちにもろもろ分析・整理して、タイミングが来たらすぐに次のステップに踏み出せるように準備しているところです。
山本:
UI/UX面では、「生成AIに対する信頼感」をどのように積み上げていくべきか、多久さんと一緒に追求しているところです。具体的には、実在の人間と会話しているような没入感を持たせたり、そこからアイデアが生まれやすくする仕掛けをシステムに入れ込むことを目指しています。
多久:
生成AIは信頼性に疑問があるという意見もありますが、試行錯誤を繰り返し、ある程度知見が溜まった私たちから見て、DAYS GRAPHYはアイデア発想に必要なインサイトを的確に得られる状態だと考えています。今後は、そのことをお客様にしっかり体感いただけるようにサービスをブラッシュアップしていきます。
── 生成AIは信頼性に疑問があるとの見方もあるなかで、生成AI技術は今後どのように発展し、私たちのビジネス面にどのような影響を与えると考えますか。
阪口:
今現在は生成AIを使った業務効率化に重きが置かれている印象ですが、今後は「いかにして生成AIを日常生活に溶け込ませながら、創造的な業務領域のサポートをさせるか」といった方向での活用も増えてくるのではないかと考えます。私たちのサービスドメインである顧客理解でも、そのジョブ自体を効率化の対象とするのではなく、創造するためにしっかり時間をかける対象としていきたいと考えています。その結果、人間にしかできない、今までになかったまったく新しい発想を生み出すためにDAYS GRAPHYを活用してもらえるところまで持っていきたいですね。
多久:
阪口さんと同意見です。DAYS GRAPHYをうまく活用されているお客様は、「頼れる存在」だとおっしゃるんです。アイデアの昇華や企画のブラッシュアップをする際の壁打ち相手として、生成AIを活用するイメージですね。「頼れる相棒」という立ち位置は、今後生成AIに求められていくと予想されますし、DAYS GRAPHYとしても目指すべき到達点です。実現するためにはどのようなユーザー体験が必要なのか、これからも突き詰めていきます。
山本:
現在は、一般的に、生成AIの活用で時間短縮を実現している状況ですが、そこで生み出された余剰時間を使って、より深く思考したり行動できるようになりますよね。生成AI誕生前と比べて人間の活動量が増えることになるので、より加速度的に技術や社会が発展していくのでは、と考えています。
田中:
エンジニアの視点でお話しをすると、プログラミングにおいて重要なのは「誰が何を求めていて、その求められているものを形にするために、自分に何ができるか?」だと考えているんですが、その過程で「生成AIが肩代わりしてくれるから、人間側でやらなくてもよくなること」が増えるのではないかと考えています。私たちの仕事が減ってしまうかも(笑)。
松浦:
例えば、生成AIを活用することで、プロンプトを入力するだけでデザインが完成したり、アプリケーションの試作品ができあがるといったことは、現段階でも十分できます。今回のような新規サービスを開発するうえでも最初の一歩を踏み出しやすくなりますし、その結果、開発側の業務は減ると思います。
しかし、実際にエンジニアの仕事がすべてなくなることはないと考えています。仮にサービスのコードを生成AIに作ってもらうとして、作成されたコードを本当に信用しきっていいのかどうか。セキュリティ面で、あるいはパフォーマンス面で問題がないのかどうか。サービスを安全に高品質に提供するためには、そういった数々の判断が必要です。適切な判断ができるよう、エンジニアとして技術の理解を深め本質を見極める力を磨いていく必要があると思います。
阪口:
当社が主戦場とするデジタルマーケティング領域において、これまでSaaSをはじめとしたツールは「効率化のための手段」として活用されていますが、その一方で、マーケターや商品開発の方々はインサイトの発見をはじめとする「探索活動」を非常に重視されています。市場が成熟し、競合商品も増え、消費者のニーズはさらに多様化・細分化していき、インサイトを発見する難易度はどんどん上がっていくことが考えられるので、「探索活動」をサポートできるツールの需要が高まってくるはずです。生成AIという技術は、探索活動にはうってつけの技術だと考えているので、それを多くの企業で活用できるように、DAYS GRAPHYを通して課題解決ができればと考えています。