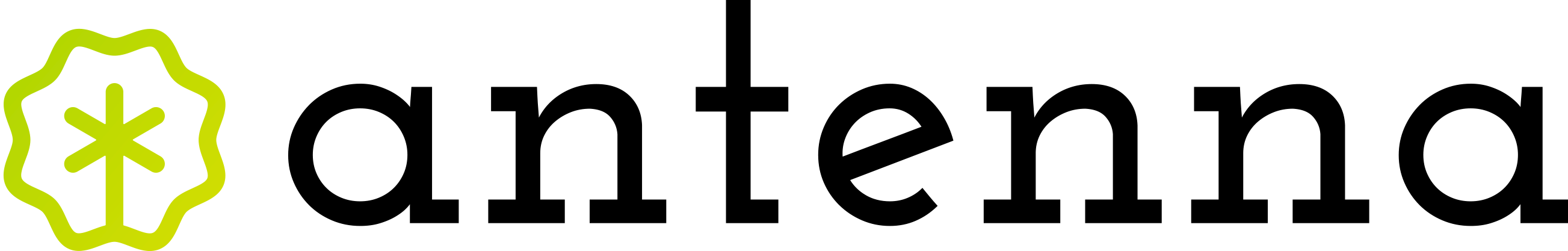この記事をまとめると
■アメリカの自動車メーカーがBEVに対する投資の見直しや新型BEVの開発中止を発表した
■アメリカ国内でもカリフォルニア州以外の地域ではほとんどBEVを見かけない
■GMやフォードはBEVを諦めたのではなく普及のスピードダウンを表明したに過ぎない
アメリカの自動車メーカーはEV開発に消極的?
アメリカGM(ゼネラルモーターズ)とフォードが相次いでBEV(バッテリー電気自動車)について大型投資の見直しや新型SUVタイプBEVの開発とりやめを発表したと報じられている。世界的にBEVの普及は踊り場にきているともいわれ、新車販売について、いままでのような勢いを失いかけているとされている。
とくにアメリカでは次期大統領を選ぶ、大統領選挙を間近に控えていることもあり、共和党大統領候補のドナルド・J・トランプ氏はすでに自分が大統領になったときには、BEVに対する税控除制度廃止を検討しているとされている。GMやフォードはこのような政治の動きと今回報じられているような動きに関係があるわけではないとしているようだが、まったく影響を受けていないともいい切れないだろう。
そもそもアメリカ政府の動きはEUなどのように、来たる近い将来にBEV以外の販売を禁止するというような前のめりなものにはなっていない。しかし、それは連邦政府レベルの話であり、アメリカのなかでもより自動車の大消費地であるカリフォルニア州では、2035年以降はICE(内燃機関)車の新車販売を禁止する(PHEV[プラグインハイブリッド車]は引き続き販売可能)としている。
そもそも今回のGMやフォードの動きは、BEVの世界的販売不振以前にアメリカ国内の事情のほうが優先しているのではないかと考える。筆者が見た限りでは、カリフォルニア州に限ってみれば、確かにBEVの普及には目を見張るものがある。州政府の風力や太陽光などによるゼロエミッション発電への積極的な取り組みなど、消費者マインドも含めてBEV普及の土台ができていることが大きいことも間違いない。
ただし、カリフォルニア以外の州ではそこまでBEVを見かけることは少ない。たとえば、アメリカンブランドの本社や自動車生産拠点の多い、ミシガン州デトロイト市とその周辺でクルマを走らせると、見かけるBEVはとにかくフォードが多かった。アメリカンブランドのお膝元でアメリカンブランドのBEVが不自然に多いとなれば、自ずと「縁故販売」に近いようなものが横行し、たたき売りされているのかなと思ってしまう。
また、フォードに勤務していて、一定役職以上でリタイヤすると、その後は毎年新車へ交換される形で、車両が会社より無償貸与されるとも聞いたことがあるので、「カリフォルニアとは売れ方が異なるな」と思いながら筆者はステアリングを握っている。
BEVのメインマーケットとなるカリフォルニア州では、大型ピックアップトラックやピックアップトラック派生のややワイルドな大型SUVなど(もちろんアメリカンブランド)、「アメリカの魂」的なモデルを除けば、アメリカンブランドより、日本や韓国、欧州ブランドがもともと強かったのだが、さらにテスラなど新興BEVメーカーも注目されている。そのため、南カリフォルニアあたりでは、BEVといえば圧倒的にテスラばかりとなり、これに欧州系や韓国系ブランドのBEVが続いているように見える。
アメリカでは外資系ブランドとなるトヨタが、全米新車販売台数でトップ争いを展開している背景には、全米における販売ネットワークの充実も大きく影響している。外資系ブランドについて、一般論では東西両沿岸部のみや、シカゴなど中西部や南部、内陸部における巨大都市で健闘する傾向がある(南カリフォルニアではとくに多い)。それはつまり、販売ネットワークと新車の売れ方が比例していると見ることもできる。
いまだカリフォルニア以外でEVを見かけることは少ない
大昔には沿岸部はフォード(アメリカンブランドのなかではより先進性があると見られていた)、内陸部はGMが強みを見せていたともいわれている。フォードより遅くまでOHCではなくOHVエンジン搭載車をGMが多くラインアップしていたのも、沿岸部や都市部より地方部では自家整備が当たり前のようになっており、高校などで自動車整備を勉強するときには、教材となる車両が古いOHV車だったので、そのまま地方部ではGMが強みを見せていたといわれている。
トヨタについてはコロナ禍前からすでに、全米の州都や中核都市ではプリウスやカムリのHEV(ハイブリッド車)も目立っていた。感度が良く一定以上の所得のある自然派ともいわれる人たちの間では、とくにプリウスに乗るのがステイタスとなっていた。
HEVがファッション感覚優先で乗られる傾向があったのだが、アメリカのなかでもとくに自動車消費市場として大きいカリフォルニアでは全米でも目立ってガソリンの高値安定傾向が続くなか、ガソリン代負担を減らしたいと考える人などがHEVに殺到するようになった。そして、そもそもHEVではトヨタはリーディングカンパニーなのでよく売れるようになり、カリフォルニアの傾向が全米の主要都市に伝わったものと筆者は考えている。
つまり、当初から日本車を中心とした外資系ブランドの販売ネットワークの弱いところで、アメリカンブランド車はよく売れていた(選択肢がほぼなかったともいえる)。しかも、地方部でアメリカ車といえば大排気量V8エンジンを搭載する(最近はダウンサイズが進んでいるが)大型SUVか大型ピックアップトラックが定番となるので、そもそものアメリカ車ユーザーにBEVが馴染みにくいという部分も、今回の投資を手控えたり新型車開発の撤回などがあるのではないかと考えている。前述したデトロイトでのBEVの話でも、アメリカンブランドの聖地のような場所なので日本を含む外資系ブランドディーラーより、アメリカンブランドの店舗数が多いことも当然あるだろう。
また、地元ではガソリン価格が目立って安く見えるのだが、これはアメリカンブランドが何らかのアシストを行っているともいわれているので、新車販売においてもこのような傾向があるのかもしれない。
BEVがよく売れるカリフォルニアでは、アメリカでありながら「なぜアメリカ車を選ぶの?」といった疑問をもたれる傾向がある。再販価値がとくに高いともいえるクロスオーバーSUVでICEであっても、燃費性能が高く、品質や耐久性能も高い日本車に比べれば著しく再販価値が低くなることも大きいようである。
アメリカンブランドも主要市場をカリフォルニアに照準を合わせて自社でBEVをラインアップしたのだろうが、そもそもアメリカンブランド車が選ばれにくい市場でもあったので、販売低迷傾向となったという側面もあるのではないかと筆者は考えている。広大な国土をもち、ひと言で語ることのできない消費傾向の違いなど、世界的な動きよりは自国内の事情のほうが大きかったのかもしれない。
だからといってBEVをまったくラインアップさせないというわけにもいかないだろう。アメリカンブランド車を嗜好する人たちの認知度などを見ながら、自分たちの得意カテゴリーはどこかを見失わずに消費者ニーズに合わせてラインアップさせていけばいいだけの話で、GMやフォードはBEV普及についてスピードダウンを表明したに過ぎないと筆者は考えている。