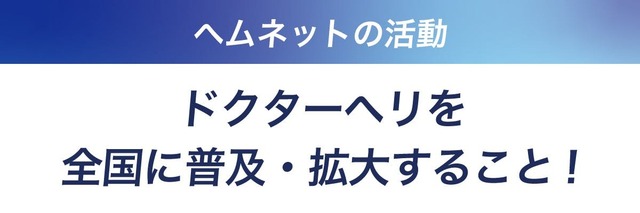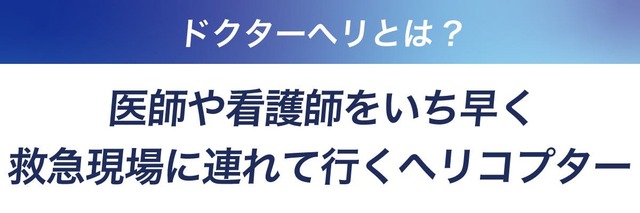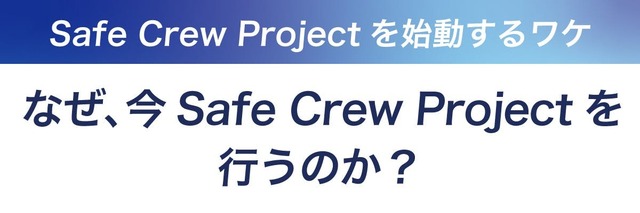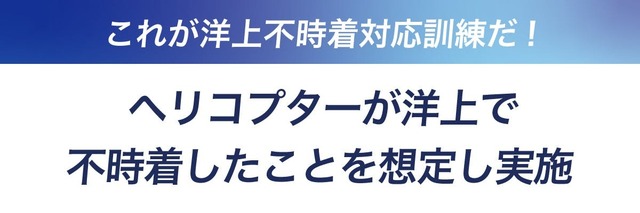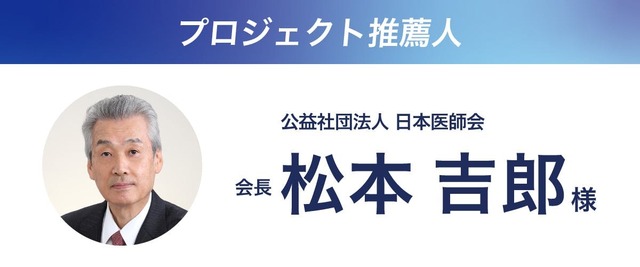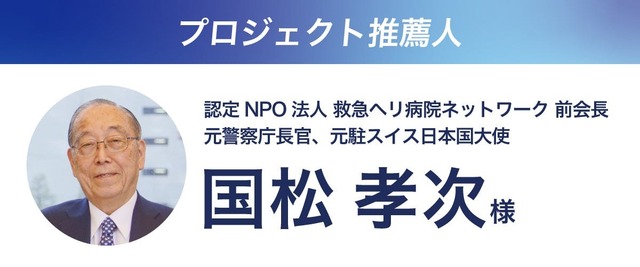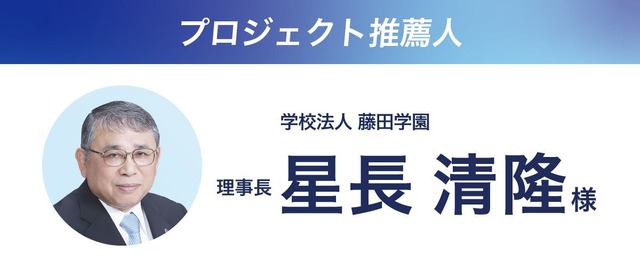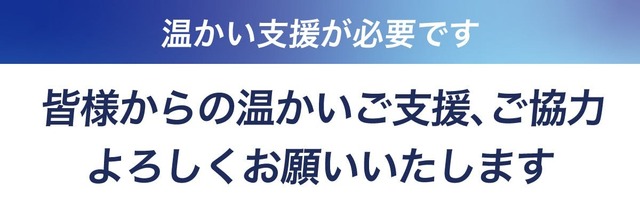2025年4月、壱岐島沖で医療ヘリが墜落し、患者や医師ら3名が帰らぬ人となりました。あの日、命を救うはずだった人々が、自ら助けを待つ立場になってしまったのです。Safe Crew Projectでは、医療クルーが命を守るために必要な訓練の費用を支援します。もう誰も取り残さないために。
救急ヘリ病院ネットワーク「HEM-Net(ヘムネット)」は、ドクターヘリを全国に普及・拡大することを目的に、1999年12月に発足した認定NPO法人です。
ドクターヘリの正式運航が開始されたのは、2001年のこと。
同年に岡山県と静岡県でドクターヘリの事業が始まり、その後、少しずつ全国へと普及していきました。そして、2024年の香川県へのドクターヘリの導入をもって、全国47都道府県でドクターヘリが運用されるようになりました。
しかしながら、「ドクターヘリは全国に存在すればいい」というものではありません。
その至上命題は「ケガ人や病人の命を救うこと」であり、そのためにはより安全に、より確実に飛行する必要があります。
そしてそれらは、ドクターヘリに搭乗する医療者の命を守ることにもつながります。
HEM-Netはこれからもドクターヘリの「質の向上」を目指し、さまざまな課題解決に向けて活動を行ってまいります。
ドクターヘリ(Doctor-Heli)とは、「医師や看護師をいち早く救急現場に連れていくヘリコプター」のこと。
機内には医療機器や医薬品が装備・搭載してあり、現場で応急処置ができる仕様になっています。
ドクターヘリは通常、基地病院(所属する病院)のヘリポートで待機し、出動要請に備えます。ケガ人や病人などが出て119番通報が消防署に入ったときに、消防から要請を受けて出動します。
パイロットが操縦するヘリに搭乗するのは、救急医療を専門とするフライトドクターとフライトナースです。基地病院から飛び立ったヘリが現地のランデブーポイント(救急車とドクターヘリが合流する場所)に着陸すると、彼らは直ちにケガ人や病人の治療にあたります。このように要請から短時間で治療を開始できるところが、ドクターヘリの最大の特徴といえるでしょう。
ドクターヘリはまた、上記のような「現場出動」のほかに医療機関から別の、より高度な医療を提供している医療機関へ患者を運ぶ「施設間搬送」や、大規模災害時での活動も重要な任務の一つとしています。
ドクターヘリが救った命の一例をご紹介します。
「あのとき迅速に診てもらえなかったら、今元気に走り回っている娘を見ることもなかった。感謝の気持ちでいっぱいです……」
こう話してくれたのは、愛知県住在A子ちゃんの母親です。
それは今から1年ほど前のことでした。1歳7カ月だったA子ちゃんは、咳や鼻汁、微熱など風邪っぽい症状 が続いていました。普通の風邪だろうと様子を見ていたところ、吐き戻しがあったことから、心配になった母親が、近所にあるかかりつけ病院の小児外来で診てもらうことにしたそうです。
A子ちゃんを診た小児科医は一言「心臓の音がよくない」と、状態があまりよくないことを母親に告げま す。肺高血圧症と急性心不全という重い病気が疑われ、命に関わる状況とのこと。一刻も早く小児の専門病院で 診てもらう必要があると判断した小児科医は、専門病院にドクターカーを依頼するとともに、基地病院にも 連絡をとってドクターヘリにも出動してもらえるよう要請しました。
連絡を受けて出動したドクターヘリの小児搬送チーム(小児救急医と小児集中治療医が搭乗)は、かかりつけ病院に到着すると、すぐにA子ちゃんへの治療を開始。最初のヤマ場を乗り越えます。少し落ち着いた段階で、ドクターカーがAちゃんを専門病院へ搬送。そこでより高度な治療が行われました。
一時期は命も危ぶまれたA子ちゃんでしたが、早期に専門的な治療を受けられたことで、翌月には退院する ほど元気に。今はきょうだいと一緒に外で懸け回る毎日です。
母親は言います。
「お医者さんや看護師さんからは、『このタイミングで気付いて、病院に来てくれてよかった』と声をかけていただいて、心強かったです。ドクターヘリって大げさに聞こえるかもしれませんが、命の見逃しを防ぐ大切な存在。多くの方にこの重要性が伝わればいいなと思います」
なぜ、今Safe Crew Project を行うのか――。それにはこんな理由があります。
2025年4月、長崎県壱岐島沖で福岡の病院の医療搬送ヘリが洋上不時着水事故に遭い、医師、患者、患者の家族の尊い命が失われるという痛ましい出来事がありました。この事故により、わが国のドクターヘリの安全を守ることが、いかに急務であるかが鮮明となったのです。
特にドクターヘリに搭乗し、日々私たちの命を救うべく活動するフライトドクター、フライトナースの安全確保は、何よりも優先されるべき課題です。万が一のことがあったときに彼らが自分自身を守り、患者やその家族の救命にあたる「洋上不時着対応訓練」は欧米では当たり前に行われているもので、日本でも早急に実施しなければなりません。
しかし、日本ではこうした訓練や安全装備に対して公的な補助はありませんし、民間の訓練施設は国内(北九州)に1カ所しかないため、地域によっては高額な交通費もかかります。今は、すべての訓練費用が個人負担になっていることから、医師や看護師が訓練を受けにくいという、厳しい現状に直面しているのです。
ヘリコプターが洋上で不時着したことを想定して行われる「洋上不時着対応訓練」。
国内でこの訓練を受けられる民間の訓練施設は、北九州市にある日本サバイバルトレーニングセンター(NSTC)1箇所だけになります。ここにはNSCT が独自に考案したプログラムがいくつかあり、その一つがフライトドクターやナースなど、ヘリの搭乗員向けの水中脱出訓練です。不時着した機体からの避難方法、および脱出に必要な技術を習得していきます。
講習は丸1日かけて行われます。午前中は座学による講習で、ヘリコプターの安全性についての知識や、不時着時に救命を阻害するリスクとなる行動、適切な行動などを学びます。そして午後は午前中の座学を受けて、実際に実技(訓練)に入ります。実技が行われる場所は、隣接する大型のプール。
受講者が乗り込み、水上や水中から脱出を図る訓練を行います。実技も終盤になると、水中で転覆した機体からの脱出など、高度なテクニックを実際に経験します。
6月25日に行われたプログラムを受講したフライトドクターの1人は、受講の理由を「長崎で起きた事故で、医療者のなかにもヘリに乗ることに不安を覚える人が出てきている」と話し、その上で「トレーニングで得た結果を持ち帰って、チームで共有したい」と話します。別の医師は訓練の終了後「これ(訓練)を受けていなかったら、(事故があっても)絶対助からなかったと思う」と感想を述べました。
今回、プログラムの受講者の中には「NSCTの存在自体知らなかった」という人も。ドクターヘリの運航にあたっては、「洋上不時着対応訓練」の周知と普及が大きな課題であることが浮き彫りになりました。
写真提供:日本サバイバルトレーニングセンター(NSTC)
救急ヘリ病院ネットワーク(HEM-Net)が行う『Safe Crew Project』
〜ドクターへり医療クルーの命を守る洋上不時着対応訓練〜を推薦し、応援します。
ドクターへり救急では、私たちの同士である医師・看護師が日々命を救うために懸命に不当しています。彼ら彼女らの安全・安心な運航体制の確立は喫緊の課題です。
HEM-Netには、何としてもこのプロジェクトを成功させ、明日の地域医療、安心できる医療体制づくりに貢献されることを念願します。
ドクターヘリに搭乗して救急救命活動に当たる医療クルーに対して洋上不時着対応訓練の受講に要する費用を助成するという本プロジェクトの意義を高く評価します。
ドクターヘリが洋上に不時着するなどということは、滅多に起こることではないかも知れませんが、しかし、先般、現実に救急活動に従事中にヘリが洋上に不時着した例が起こりました。
安全の確保に資格があることは許されません。万万が一に備えて常時訓練を積んでおくことの重要性を強調して、しすぎることはありません。
本プロジェクトが、多くの方々の支援を得て充実した形で実施され、ドクターヘリの安全運航の確保に資するものになることを期待いたします。
医学大学として、次世代の医師・看護師の育成に携わる私たちは、現場での安全教育の重要性を強く認識しています。認定NPO法人救急ヘリ病院ネットワーク(HEM-Net)による「Safe Crew Project」は、ドクターヘリに従事する医療クルーが洋上不時着時にも安全を確保できる力を養う貴重な機会です。教育機関の立場からも、本プロジェクトの意義を深く支持し、多くの方々のご賛同とご支援を心よりお願い申し上げます。
川崎医科大学 救急医学 講師
川崎医科大学附属病院 救急科 医長
高橋 治郎 様
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この度は大変お世話になっております。昨日は大変貴重な機会を頂きありがとうございました。本講習を通し、普段医師として業務に当たるだけでは見えていなかったリスク、また事前の備えについて考えることができました。自施設や他の講習会の場でも、経験を踏まえた指導に当たりたいと思います。
愛知医科大学病院 救命救急科
寺島 嗣明 様
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
お世話になっております。大変貴重な機会を頂きありがとうございました。
有意義な機会となり感謝しております。今後ともよろしくお願いいたします。
HEM-Netは、ドクターヘリに搭乗する医療クルーを対象に、洋上不時着対応訓練の受講費を支援する取り組みを行っています。
みなさまからの支援金は、以下の用途に大切に使用します。
・洋上不時着対応訓練の受講費支援(1人あたり約5万円)
・訓練用の装備などにかかる備品費
・広報活動費(SNS発信・動画制作費など)
※資金管理は、第三者を含む運営委員会のもとで透明性をもって行い、活動報告書にて結果をご報告いたします。
読売新聞オンラインの記事でも紹介されました。
2025年6月 訓練開始(第1期)
2025年7月 クラウドファンディング開始
2025年7月以降 訓練開始(第2期〜)
▶︎インターネットからご支援が難しい方へ
下記リンク先(HP特設ページ)にて振込先口座を掲載しています。
銀行・ゆうちょ等から直接お振り込みいただけますので、ご都合に合わせてご利用ください。
SafeCrewProjectクラウドファンディング特設ページはこちらです。
▶︎税制上の優遇措置について
本プロジェクトへのご寄付は認定NPO法人 救急ヘリ病院ネットワーク(HEM-Net)への寄付となり、弊団体が寄付金の受付及び領収証発行を行います。このプロジェクトの寄付は寄付金控除の対象になります。「寄附金控除」をお受けいただくためには、確定申告の際に、(団体名)が発行した領収証をもって確定申告をしていただく必要がございます。領収書の発送時期は法人の場合は、入金確認後1ヶ月後、個人は12月中旬予定しております。※領収証はCAMPFIREではなく当団体が発行いたします。
▶︎CAMPFIRE For Social Goodについて
このプロジェクトは、支援者さまからのご協力費(12%+税)により運営しています。
「私達の命を守る人の命を守る」ため、ドクターヘリに搭乗するフライトドクター、フライトナースには洋上不時着対応訓練が必要です。皆様の温かいご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。