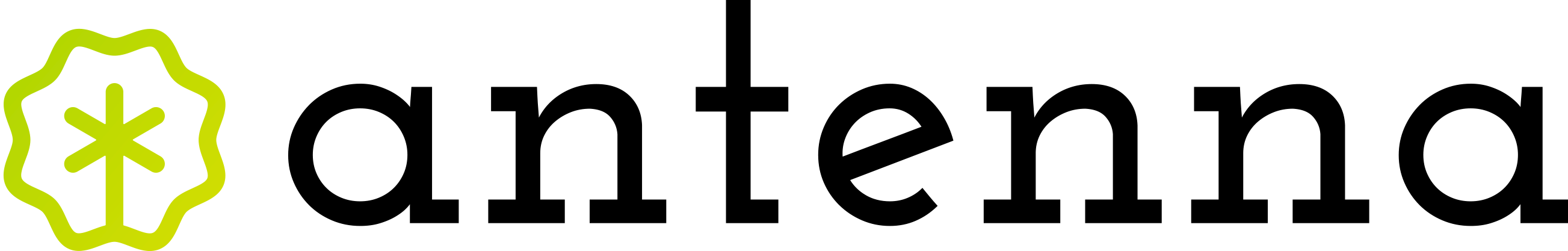この記事をまとめると
■レーシングカーには変わったボディタイプをもつマシンが多数存在する
■とくにワゴンボディのマシンは多くのカテゴリに投入され活躍した
■プロトタイプレースカーにも奇抜なボディメイクのマシンがあった
各カテゴリで意表を突いたワゴンボディのレースマシンたち
自動車の誕生からそれほど時間を置くことなく自動車レースは始まっている。そして、時代とともに自動車は進化を遂げてきたが、大きな流れとして捉えると、やはり量産車をベースとするカテゴリーが中心となって現在にまで続いている。というより、やはり自動車の原点は量産車にあり、サーキットレースにおけるフォーミュラやスポーツプロトタイプは、車両の形態が量産車から進化、発展を遂げたものと考えてよいだろう。
さて、量産車ベースのレース車両だが、大きくふたつのカテゴリーにわけて考えることができる。ひとつは、長らく実用性を軸に自動車(量産車)の原点と考えられてきたセダン(サルーンカー)によるツーリングカーレース、そしてもうひとつが走りに特化したスポーツカーの考え方をベースにするGTカーレースである。
おもしろいのは、こうした量産車ベースのカテゴリーで、時折「おやっ」と意表を突くモデルが登場したことだ。1990年代にツーリングカーカテゴリーに登場した「ワゴンボディ」車の存在は、ツーリングカー=セダンというこれまでの常識、固定観念を覆すものとして新鮮であった。
まず、真っ先に登場したのがボルボ850TSエステートだ。それは、グループA規定の後を受けて発足した「クラス2」ツーリングカー規定下の1994年のことだった。戦闘力の接近化を図って1982年に実施されたグループA規定は、最終的には勝てる車種が特定される流れとなって消滅し、かわって2リッター自然給気エンジンを使う「クラス2」ツーリングカーの規定となっていたのだ。
850エステートがレースシーンに登場を飾った舞台は、数あるヨーロッパのツーリングカーレースシリーズ中でも、もっとも権威があると受け止められていたBTCC(ブリティッシュ・ツーリング・カー・チャンピオンシップ)だった。FRからFFへ。駆動方式、パッケージングも含めて車種ラインアップの刷新を図っていたボルボ社は、新シリーズ規定の850エステートによってレース参戦を企画。レースに参戦し活躍することは、市場に対して大きなPR効果があることを熟知していたからだ。
850エステートのクラス2仕様車を開発し、走らせたのはTWR(トム・ウォーキンショー・レーシング)。1980年代にグループA(ジャガーXJ-S)、グループC(ジャガーXJR-6~XJR-15)を走らせ、1988年にはジャガーに31年ぶりのル・マン制覇をもたらした、イギリスでも屈指のレーシングコンストラクターである。
そのTWRは、市場に対するインパクトが大きいという理由により、ボルボ社から850エステートによるクラス2ツーリングカーの開発・製作を依頼されたわけだが、セダンボディと徹底的な比較検討を行った結果、ワゴンボディで行けると判断され、1994年のBTCCシリーズに臨む運びとなった。
車両は、時間が足らず十分に開発・熟成されなかったためなのか、全戦(13サーキット/21レース)に参加して最高位は5位。シリーズランキングは10メイクス中8位と残念ながら満足のいくものではなかったが、ワゴンボディがファンに与えたインパクトは大きく、ボルボの名前を強く印象付けることに成功していた。
日本車も変わり種ボディをもったレースカーの宝庫!
サーキットレースへのワゴンボディの投入は、じつは日本のサーキットでも行われていた。2006年、スーパー耐久ST-2クラスにランサー・エボリューション・ワゴンが登場。
2005年9月にリリースされたランサー・エボリューションⅨのワゴンモデルをベースとしたマシンは、セダンモデルと並行してスーパー耐久シリーズに出場。ボルボ同様、ワゴンボディでも十分レースに耐える性能を備えていることをアピールするため投入されたのである。結果的にはほんのひと息、セダンにおよばなかったが、高性能を備えることは十分に実証した。
その性能がセダンボディと遜色がないことを示すように、ワゴンボディのマシンはラリーフィールドにも投入されていた。
それも世界レベルでの戦い、1995年のサファリラリーにグループN規定車両で参戦が行われたのである。ドライバーは日本人の三好秀昌。この年のサファリは、WRCの冠タイトル戦から外されていたがグループA車両が多数参加していたのである。
勝ったのはグループAセリカGT-FOURの藤本吉郎、2位はグループAランサー・エボリューションIIIの篠塚建次郎だったが、三好秀昌の操るインプレッサ・ワゴンは、グループN車両ながら総合4位、クラス優勝を勝ち取っていた。インプレッサには同型のバンがなく、ワゴンモデルのステータス性は高く、こうした意味でのPR効果は十分に得られていた。
一方、サーキットレースで独創的な形の車両はないかと振り返ってみると、つい最近(といっても10年以上も前だが)きわめて特徴的な車両が1台だけあった。ル・マン、WECがハイブリッド・プロト時代になった初年の2012年、賞典外参加のかたちでル・マンに参戦したデルタウイング・ニッサン。前がすぼまり後ろが広がるフォルムをもっており、その形から日本人ジャーナリストから「イカ」と呼ばれたマシンだ。設計はデルタウイング・レーシング・カーズのベン・ホヴルビーが執り行った。
エンジンは1.6リッター直列4気筒直噴ターボの日産MR16DDT型を搭載。出力は300馬力と非力だったが、420kgという超軽量な車重によって3分42秒612とLMP2クラスと遜色ないタイムをマークした。決勝では他車との接触でリタイヤに終わったが、車両概念を変えれば、驚くほど効率的に性能が確保できることを実証。残念ながら本格的な参戦活動はこの1年で終了してしまったが、可能性を見せたという意味では、非常に大きな参戦意義をもつ「変わり種」の1台だった。