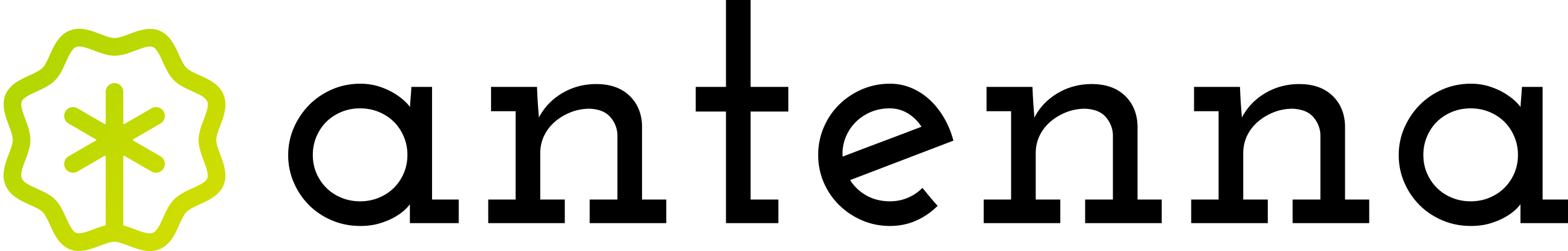この記事をまとめると
■マツダCX-80の日本仕様が公開された
■車両を担当した玉谷 聡さんにインタビュー
■CX-80のデザインについてお話を伺った
いままでのマツダ車とは異なる豊かなデザインを追求
2024年秋の発売が見込まれている、マツダの新たな3列シートミドルラージSUV「CX-80」。メカニズムのみならずフロントドア以前の外板も、2列シートの「CX-60」と多くを共用する制約があるなかで、いかに独自のスタイルを構築していったのか。デザイン本部の玉谷 聡主査に聞いた。
──今回のCX-80では、フロントセクションをCX-60と共用するという制約があったので、エクステリアデザインは非常に難しい点が多かったのでは……?
玉谷 そうですね、なかなか難しかったですよ。私、最初は乗り気ではありませんでした。
──(笑)
玉谷 難しさが手に取るようにわかっていたので。CX-60もナロー版のショートボディで、幅があればもっとスポーティにできるんですが、商品の市場適合性を考えると全幅1890mmがギリギリだろうということになりました。CX-5やCX-8の全幅1850mmに対し、CX-60やCX-80は40mm広がっていますが、室内幅も同様に広がっているので、エクステリアの造形しろはじつは増えていないんですね。苦しかったんですよ。
ですが、CX-60は短い全長のなかでなんとか研ぎ上げたと思います。しかし、CX-80はその全幅が狭いまま、ダックスフントのように胴体だけが250mm伸びるというのを聞いたので、「ちょっとこれは難しいぞ。できればほかの人がやってくれないかな」と思ったんですが(笑)。
プレゼンテーションのなかで、CX-5からCX-8のようにそのままスポーティさを維持するのではなく、CX-60からCX-80を構築するにはそのままではダメで、3列空間の広大さをしっかり表現するよう発想を転換したことをご説明しましたが、その切り替えがなければモチベーションが上がらなかったですね。
いわゆるクルマの格好よさは、幅があるほうが格好よく、背が低いほうがスポーティということになりますが、CX-80のようなクルマはそれとは全部逆行します。
パッケージング設計担当の高橋とは、開発の前半で火花を散らして、「あと10mm叩け」「シルエットのスピード感が大事なんだから」といった話をするんですが、今回はそれをしていっても、格好よさの方程式に当てはまるスタイリングにならないことを直感したので、発想を変えようということになりました。
マツダが美しさや格好よさを表現していくなかで、マツダ車にはない豊かな強さやおおらかさがあると思って見たのは、BMW傘下になる前の、エレガントだったころのロールス・ロイスだったんですね。ボディとキャビンの面の作り方が非常におおらかで、大きな面をピチッと綺麗に作り上げている。それを、クルマの全長よりも長い面のコントロールがそこにはあり、ボディとキャビンがそれぞれ調和しながら少しずつねじれていくのが、豊かな強さに見えたんですね。
ですが、それはそのままマツダのクルマには絶対に当てはまらないと思っていたんですが、今回マツダ車のなかでもっとも大きなクルマを作るとなったときに、サイズがアップしていくと、そのサイズなりの車格を表現する豊かさが必要だと思ったんですね。従来のマツダ車にはないサイズと存在感になってくるので、視点を変えなければいま我々がもっている方程式では対処できないなと。
そこで、以前より思い描いていたものを、マツダ車の方程式に少し当てはめてみて、これまでとは違う答えを出してみようと思ったんですね。
それを「直線的」「建築的」という言葉で表したんですが、これまではキャビンを叩いて叩いてスリーク(洗練された)にし、スピード感を表現していたのを、逆にそこにある空間を大きく出すことで、違う迫力を出そうと。
そこでは高級車のおおらかな高さを出して、せかせかしているのではなくどーんと、人生を楽しんでいるような豊かさがほしいと思って、開発チームメンバーにも「視点を変えよう」と、いままで描いたことがないような、ちょっと行き過ぎたものもいろいろ描いてもらったんですよ、自分たちで既成概念を壊していかなければならないと。
それと同時にやはり動体美学、マツダ車の走り、コーナーを曲がっているときの座りのよさを失ってはならないので、その範疇でバランスして、いままでのマツダ車にはない、だがマツダ車ではないという踏み外したものにはなっていないようなバランスを探して作ったのが、今回のCX-80のエクステリアです。
そのバランスはなかなか絶妙なものなので、それをひねり出していくのはモチベーションが上がりましたね。
──フロントのドアパネルまで形が決まっているなかで、そこから後ろを完全に作り替えるとなると、前後を調和させるのがとても大変だったのでは……?
玉谷 そうですね、じつはリフトゲートも流用なんですよ。前半分はCX-60、リフトゲートはCX-70とCX-90のものを流用しつつ位置は調整して、リヤコンビランプも法規上一部異なりますがCX-70とCX-90のものを装着しています。
ですから、造形の始まりと終わりが決まっているなかで、その間を作っていく、それが絶対に不自然にならないように作っていくバランス感覚、練り上げていく質感の調整が、かなりテクニックも要りますし、経験値もないとできないことですね。
──ボディサイドの「光の移ろい」は、CX-60よりも深くなったように見えました。
玉谷 じつは深くはなっていないんです。が、長く引っ張っているんですね。リヤドアは160mmくらい長くなっているんですが、しっかりと光を動かしながら、ドアの構造要件を成立させるのは難しかったですね。
「光の移ろい」には始点と終点がありますが、クルマを動かすことによって動く光はクルマの角度で決まりますので、「光の移ろい」の移動時間は一緒なんですよ。ですが、移動距離が大きくなるので、光の動きはCX-60よりも早くなって、ダイナミックに大きく動いているんですよね。そういう大きさによる迫力は、CX-80のほうがあると思います。しっかり光を動かしているので、光の深みが立体的にあるように感じていただいているのだと思います。
グリルのアクセントで差別化を図った
──CX-80はパッケージング的に、綺麗なプロポーションが取りにくいとは思うのですが、たとえばメルセデス・ベンツGLBのように完全な箱にしてしまうか、もしくはサイドウインドウの天地をCX-8以上にうんと薄くする方法も考えられたと思います。そこはあまり極端に走るのではなく、バランスを取りたかったということでしょうか?
玉谷 ボクシーな絵は少し描いてみましたが、マツダの走りを表現するようなCX-60のフロントがあるうえで、その後ろに箱を付けたような形にはできないと、一瞬で判断しましたね。
また、薄いウインドウというのはこれまでの方程式ですし、極端に薄くしていくと乗員に必ず閉塞感を与えるので、これは自然な豊かさにはならないと思っていました。
「乗ってみたいな」と思わせる、外から見た豊かさと、乗ったときに「やっぱりこの空間はいいよね」と感じていただけるものを合致させなければならないので、窓枠を少し大きくしています。
3列目にも専用のサイドウインドウがあって、前方を見たときに視界がパノラミックに広がる雰囲気があり、サンルーフも面積が大きくなっていますので、それが開放感として機能します。
そういう意味で、空間を豊かにしたかったので、今回のCX-80のようなバランスになりました。
──新型車が発売されたときに一般ユーザーがとくに楽しみにするのは、フロントマスクとインパネのデザインだと思うのですが、それをなぜCX-60とCX-80とで共通化することにしたのでしょうか?
玉谷 CX-60とCX-80、また北米向けのCX-70とCX-90、この4車型で考えていますが、これをマツダの企業体力できっちりフィニッシュさせていこうとすると、少しは効率性を上げなければなりません。また、CX-60とCX-80では人格といえるボディをしっかり変えているんですね。ですから無理にフロントを変更していません。リソースが有り余っていたら差別化したかもしれませんが、今回はそこにはエネルギーを使っていません。
また、CX-70とCX-90では、メタルの部分がまったく一緒なんですよ。同じボディで2列シート車と3列シート車を作っています。そこで性格をしっかり変えるために、こちらでは前後バンパーのデザインを差別化していますね。
お客様からすれば、差別化してほしいというのは理解できます。私もそうですので、CX-80はグリルにアクセントを付けています。
長いモデルライフのなかで、我々のビジネスが成長し成功していけば、CX-60とCX-80の性格をもっと明確に変えていこうということになるかもしれません。
インテリアもCX-60とCX-80とで一緒なんですよね。マツダは商売があまり上手ではないところがあって(笑)、CX-60だけにあれだけのバリエーションを用意するのは多過ぎですよね? あれもラージ商品群にしっかり分配していくという流れのなかで開発したすべてのインテリアなんですが、最初に全部出してしまって(苦笑)。
ただ将来、CX-80を発売する際に、フラッグシップとして認めていただける質感を作り込んだものが最初からあって、それをリリースしたということですね。
ですから、CX-80に向けてさらに新たなものを追加するのは体力的にも難しかったですし、もっと上手な出し方はあったと思います。
──ボディカラーとしてはメルティングカッパーメタリックが新色として設定されましたが、実車で見るとフラットな質感に見えました。最近のマツダ車の特徴である「光の移ろい」が感じにくい光の出方をしていると思うのですが、それはメタルの粒子が細かいからでしょうか?
玉谷 フラットな見え方は意図しているものではなく、恐らく車両が置いてある環境ですね。今日(2024年6月7日。取材時点の天気は雲の多い晴れ)のような曇り空では乱反射した波長の光がふわっと全周から集まってくるんですよね。そうなると恐らくどんな色でも本来の実力は出せていないと思います。
メルティングカッパーメタリックは、白いヴェールがうっすら被ったような質感も、アルミフレークの細かさから出ているんですが、それでカッパーを生々しく見せない、ちょっと新しい質感になっているんですね。シェードでは少し黒い色で落ちますが、いろんな光でいろんな表情が見えるのも、あの色の強みだと思っています。
──フロントフェンダーに「INLINE 6」といったエンブレムがCX-80には装着されていますが、ああいったエンブレムは、デザイナーさんの視点ではどうなのでしょうか?
玉谷 最小限にしたいですよね。表現すべきものは表現するけど、いろんな技術を入れるたびにひとつずつ増えていき、バッジだらけになるのは好ましくないですね。
──バッジ自体のフォントやデザインもこだわって作られているのでしょうか?
玉谷 そうですね。文字やマークは共通でデザインする者がいますので、チーフデザイナーと協議しながら作ってもらっています。デザイン本部内でCIに関わる文字を司るブランドスタイル部があります。
──CX-80のようなクルマでも通用するものにしなければダメだということですね。
玉谷 はい。文字やマークを決めるときは、Bセグメント車からラージ商品群までイメージして討議しながら決めます。
──マツダさん全体で、今後「匠塗」のさらなるバリエーション展開はあるのでしょうか?
玉谷 「匠塗」は少しずつ広げていくと思います。
──現時点では赤系が中心で、グレーとパールホワイトがあるという展開ですが、青系やカッパーのような金属系の色も合うのではないかと想像しますが……。
玉谷 でも急激にバリエーションを拡大することはしないと思います。これまでソウルレッドやマシーングレーという限定的な範囲でスタートしたのは、やはりブランドの軸をしっかり表現する、どの「匠塗」でもマツダのブランドを象徴する色というイメージにしようという狙いからです。パレットのように多くの色があると、イメージが散漫になるんですね。
その軸をとおしたうえで、どの色にも共通するものを感じ取っていただけるようにしなければ、ブランドサポートカラーにはなりません。メルティングカッパーのようにキャラクターを増やしていくうえで上質なものはこれからも作り続けていくので、そこは使いわけていくと思います。
ブランドサポートカラーは、いまから10数年経っても使っていける種類の範疇に収めていくと思います。
──発売後の進化も期待しています。ありがとうございました!