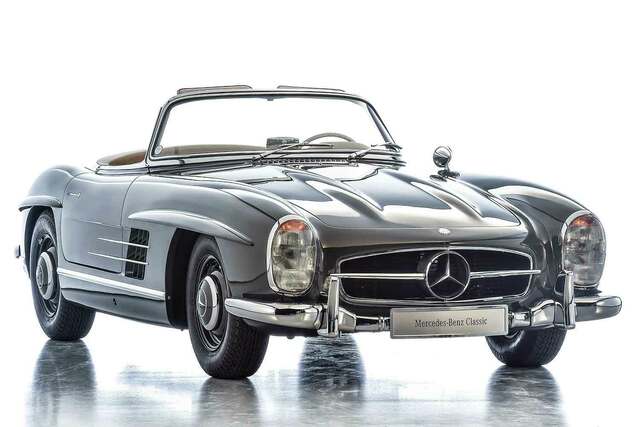この記事をまとめると
■かつては当たり前の装備だった「ハロゲンライト」のよさを解説
■ライトの色温度がLEDよりも低いので目に優しい
■発熱するので雪に強く交換作業も簡単に行えるというメリットもある
LEDヘッドライトの採用が増え続けている
スマホやパソコンの世界の技術の進化は日進月歩で、いまや半年も情報のキャッチが遅れると、取り返しが付かないくらいの遅れとなってしまうことも珍しくありません。クルマの業界もそれは同じで、15年くらい前までのヘッドライトは「HID(高輝度放電ランプ)」が主流でしたが、いまや軽自動車を含めて多くの車種に「LED」が採用されています。そして昨今では「レーザービーム」なんていう新たな方式のヘッドライトが登場しており、まだ高級車など一部にしか採用例はありませんが、順次下のクラスにも普及していくでしょう。
そうして新型車には以前のものよりも高い性能を備えたものがどんどん採用されていき、古い技術のものは採用されなくなって廃れていくという大きな流れがあります。しかし、古い技術の製品が、すべての面で劣っているかというと、けっしてそうではありません。
ここでは、世代でいうといまのLEDよりも2世代も前となってしまった「ハロゲンランプ」にスポットを当てて、そのよさを掘り起こしてみようと思います。
■自動車のランプの歴史で見ると、ハロゲンは新しいほうかもしれない
はじめに、ザックリと自動車用ヘッドライトの歴史を振り返って見ましょう。
・アセチレンランプ
最初に自動車用ランプとして実用化されたのは「アセチレンランプ」と呼ばれる燃焼型のランプでした。登場は1900年代初頭。原理はアルコールランプと同じで、燃料を燃焼させて発生した光で前を照らすというものです。アルコールよりはるかに激しい光を発するアセチレンを使用してレンズで収束させることで、それなりに実用性の高いヘッドライトだったようです。
・白熱球
アセチレンランプの実用化から10年後の1910年頃には、電気をフィラメントに通して発光させる「白熱球」タイプのランプが登場します。ただ、この当時はまだダイナモ(発電機)が登場していなかったので、電気を溜める蓄電池を積んでその電力を使って照らしていたようです。
・シールドビーム
徐々に自動車にダイナモが搭載されるようになり、電気式のランプが普及してくると、よりシンプルで頑丈な構造の「シールドビーム」が登場してきます。これは自動車のヘッドライトの用途に特化した形状とシンプルな一体型の構造をもっていて、省スペース性にも優れていたことから一気に各国のメーカーに採用例が増えていきました。
登場は1940年ごろですが、それから30年以上にわたって自動車用ヘッドライトのスタンダードとして使われ続けていました。
・ハロゲンランプ
一体型による交換のしやすさなどから広く普及したシールドビームですが、その原理は家庭の白熱電球と同じなので明るさはそこそこというレベルなのに加えて、フィラメントの劣化や振動による断線などで球切れとなるケースがそれなりの頻度で起きてしまうのが宿命でした。
そこで1960年頃に新たに登場したのが「ハロゲンランプ」です。基本構造は白熱電球と同じですが、電球の中に封入したハロゲンのガスの効果でフィラメントの劣化が防げるようになったので、より高い温度で稼働させることができるようになり、明るさが格段に増しました。
普及して性能が安定したころのハロゲンランプは、60Wの消費電力で、白熱灯の100W相当の明るさが出せるという売り文句で性能がアピールされていて、実際に装着した際にも段違いの明るさを見せていたので「あながち嘘ではないな」と評判になり、当時のカー用品店のヘッドライト関連コーナーの棚にはかなりの数の製品が並べられるほど人気を博していました。
その後は2000年頃にHIDランプが登場し、ハロゲンランプは廃れてしまいます
■ハロゲンランプに優位な部分はあるの?
ヘッドライトの歴史を振り返ってみると、世代が変わるごとにその明るさは確実に向上しています。むしろその前方を照らすというヘッドライトの役割を考えると「明るさこそ正義!」といっても過言ではありませんが、実際にいろんなシチュエーションで運転してみると、ただ単に明るければいいとは限らない、という認識をもっているドライバーも少なからずいると思います。
たとえば「視認性」で考えて見ましょう。ハロゲンランプの特徴のひとつは、色温度が低いという点です。「色温度」というのは熱で発光するときの温度と発光色の関係を表す基準です。物体やガスは温度が上がるとその発光色が変化します。鉄を溶かすシーンを思い浮かべてもらうと真っ赤に発光していることと思います。鉄が溶ける温度がだいたい800度くらいで、そこからさらに温度を上げていくにつれて明るくなり、約5200度くらいでは色が白になります。そしてさらに温度を高くして1万度付近になるとその発光の色は青白くなります。
これを電球で見てみると、ハロゲンは黄色寄りの白色で、HIDは青白い色味になっています。色温度を表すケルビンという単位では、ハロゲンは4000〜6000K、HIDは5000〜8000Kといった感じでしょうか。
ちなみにこのケルビン数は明るさとは別の基準なのですが、熱光源のランプの場合は温度と明るさがほぼ比例しているので、明るさ(ルーメン)が増すとケルビン数は高くなる傾向です。
さて、そのケルビン数が低く、色味が黄色寄りのハロゲンランプですが、ケルビン数が低いとどんなメリットがあるでしょう?
ひとつは目に優しいという点です。ヘッドライトの役割は前方を照らすことなので明るい方がいいというのは当然なのですが、逆に照らされる側になってみると、HIDやLEDの強い光は、人によっては目を攻撃されたかのようにまぶしさを感じます。暗ければまぶしくないのは当たり前と言うなかれ、明るすぎるライトには照らされる側の被害を含んでいるというのもまた事実なのです。
もうひとつは「視認性」の点です。通常の夜間の走行時については、ヘッドライトが明るいほど前方がはっきりと見えて、遠くまで物体が確認できます。しかし、雨が降っているときは路面の反射が強くなり、逆に視認性を低下させてしまうシチュエーションもあります。そういう場面では光が強すぎず色温度も程々なハロゲンランプのほうが適していることも十分あり得ます。
また、たまに遭遇する濃霧のシチュエーションではそれが顕著に表れるでしょう。霧というのは水の細かい粒子が舞っている状態なので、光を乱反射させる働きを持っています。そこに強い光を当てると、前方に通らないばかりか、乱反射の強さと範囲が大きくなり、まるで前方に光源があるかのように視界が阻害されてしまうことがあります。これは霧が濃いほどひどくなります。
ハロゲンランプは光が強すぎないので乱反射の範囲が少なく済むということに加え、色温度が低いので乱反射に紛れず遠くまで光が届きやすいという特性があるんです。フォグランプの光が黄色いのもその理由からです。
そしてもうひとつ、ハロゲンランプならではのメリットがあります。
それはヘッドライトに雪が積もりにくいという点です。ハロゲンランプはHIDやLEDに比べるとランプ自体の発熱量が高いという特性を持っています。そのため、点灯している状態では温度が高く保たれるため、付着した雪を溶かして積もりにくくなるのです。
これは一部の豪雪地域の人だけが得られるメリットかもしれませんが、せっかく明るい光を発しても、雪が積もってしまっては前方を照らせませんので、これはこれで確かなメリットといえるのではないでしょうか。
■扱いがカンタンという面もある
これは性能面でのメリットではありませんが、ハロゲンランプはHIDと比べて扱いが容易だという点もメリットに数えていいのではないでしょうか。
ハロゲンランプはシンプルな電球のカタチをしているため、脱着の際はカプラーを外して電球を抜き、新たな電球を差し込んで固定してカプラーを戻すだけで済みます。
ちなみに標準的なH4タイプのハロゲンランプはハイ/ローの電球が一体型の構造なので、いまどきのハイ/ロー別々のLEDライトに比べても交換作業は容易と言えるでしょう。
こうして「ハロゲンランプ」のメリットを挙げてみました。一部の限られたユーザーにはまだまだメリットは存在するといっても差し支えないとは思いますが、やはり明るさの面でのビハインドはいかんともしがたく、一般の多くのユーザーにとっては「やっぱり明るいのは正義!」という結論に落ち着いてしまうかもしれません。それでも「ハロゲンランプ」がなくなってしまうのは寂しい限りですので、個人的に「旧いクルマにはハロゲンがオススメです」といい張っておきます。